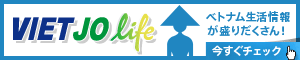それぞれの故郷に帰ってからも、2人は悲しみを引きずり続けた。そして何カ月かが過ぎ、チンは家を出てフーンを探しに行くことを決心する。彼女の「さよなら」がどうしても信じられなくて、彼は来る日も来る日も彼女を探し続けた。
2003年10月のある朝、フーンがベッドに横になっていると犬が鳴く声がするので振り返って見ると、そこにはチンがいた。彼女は起き上がって彼を抱きしめたかったが、体が動かない。チンはフーンをしっかりと抱きとめ、2人は子どものように泣いた。フーンの父母は突然の出来事にただあっけにとられるばかり。
「私たちははじめ彼のことを疑いさえした。今の時代にこんな奇特な人がいるなんて誰が信じられるだろう。元気な娘ならともかく重い病気を患っている娘を追って、南部からわざわざこんな所まで来るなんて・・・」。フーンの父親がこう語ると、チンは目に涙を浮かべながら、「ベッドに横たわる姿を見た時、それが彼女だとはとても信じられなかった。離れていた4カ月の間に47キロあった彼女の体重は30キロにまで減っていて、その姿は変わり果てていた」と振り返る。
フーンは明るく笑い、「何が起ころうと楽しんで生きていくわ。なによりも、愛する人がここにいるんだもの。私は世界一の幸せ者よ」と力強く言う。 チンが傍らでこんな歌を歌った。「もう泣かないで、僕がそばにいて涙をぬぐってあげよう。そしていつまでも一緒に生きていこう。僕の君への想いが、君を幸福の国へ導くように・・・」
それ以後チンはフーンの家に住み、畑仕事や家畜の世話を手伝って過ごしている。そしてどんな時もつきっきりで彼女を看病し、独学で学んだマッサージをしてやったりしている。時には歌を歌ってあげたり、面白いことを言って笑わせたりもする。
庭に咲く花を眺めながら、フーンが言う。「紫色は誠実の色よね?まるであなたみたい」。2人はほほ笑み合い、「私たちの気持ちをどんな言葉で表せばいいのかしら。考えてもらえません?」と私に言い、最後にこう付け加えた。「ただ、あまり先が長くないから、急いでね」

 から
から



)

)

)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)