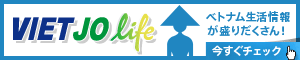) (C) danviet, ディン・ティ・ホアン・ロアンさん |
やがて妹が小学校に入学し、嬉しそうに学校に通うのを見て、ロアンさんは「自分も学校に行きたい」と母親に訴えた。それを聞いて母親はただ黙っているしかなかった。彼女は当時を振り返った日記でこう記している。「母は私を抱きしめ、お前が学校に行けるはずがないでしょうと言った。どうして?と聞いても、ただ黙っているだけで答えない。学校に行けたらどんなにいいだろうと想像した。たまに妹が家に本を置き忘れているのを見つけては、中に書かれた文字を眺めた。この文字が読めたらいいのに・・・」
妹は聡明で活発な子供だった。毎日学校から帰ると、友達を誘って縄跳びなどをして遊んだ。それらは当然ロアンさんにはできないことだった。そしてある時、どういうわけか、妹はロアンさんを生徒役にして「先生ごっこ」を始めたのだった。学校の先生がするように、一文字一文字繰り返し読み、学校に行けない姉に教えるようになった。
ロアンさんも必死で覚えようとした。家族が寝静まるのを待って、妹の本を取り出し復習した。妹が韻を組み合わせて単語を教えると、ロアンさんもそれに倣って言葉を発した。こうして妹はロアンさんにとって人生で最初の先生になった。1か月ほど経つと、ロアンさんは徐々に文字を読むことができるようになっていった。その時から、彼女の世界は格段に広がったという。
文字が読めるようになると、今度は無性に書きたくなった。彼女は曲がった指と手のひらを使ってやっと鉛筆を掴むことができる。言うのは容易いが、実際に書くためには肩を上下に動かさなければならないので大変な作業だ。彼女の書く文字は子供が書いたようなバランスの悪い文字だが、その一つ一つが彼女の汗の結晶だ。書くことができるようになり、彼女の人生はさらに明るくなった。
母親はこう語る。「20歳になってようやく車椅子にも乗れるようになりました。以前から昔話を聞いたり、詩を読んだりするのが好きな子供でした。テレビを見るのも好きで、とくに自然の風景が映し出されると食い入るように見入っていました。だからと言って、詩を書くようになるとは思いませんでしたが・・・」

 から
から



)
)
)
)

)

)
)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)